こんにちは! 作家・教育ジャーナリストの佐野倫子です。「アラフィフになって働きながら&育児と並行して大学院に通ってみたい」というふんわりとした思いつきをリアルにするまでの顛末を書きたいと思います。3回目は、「超短期決戦の受験準備編」です。
Contents
東京大学大学院はハードルが高かった
46歳、中学生と小学生2児の母が「仕事しながら大学院に行ってみたい」と考えて深夜に検索を繰り返すこと数ヶ月。思い切って東京大学大学院の説明会に参加しますが、準備不足や仕事との両立を考えるとすぐに挑戦するのが難しいと痛感したのは前回まで書いたとおり。
しょんぼりしながらも、諦めきれずにさまざまな入試情報を調べるうちに、「東京大学大学院情報学環教育部」なるものを発見します。
私はメディアや情報社会学に近い学部で学びたいと考えていたため、東大の情報学環という学府を調べていたのですが、どうやらそこの一部のようです。さっそく見てみると以下のように書いてありました。
情報学環教育部とは?
情報学環教育部は、情報、メディア、コミュニケーション、ジャーナリズムについて学びたい人々のために、おもに学部レベルの教育を2年間にわたっておこなう、ユニークな教育組織です。講義は、各自が所属する学部の授業などと両立できるように、おおむね午後から夜間にかけて開講されています。
学部、研究科という「タテ糸」で成り立つ東京大学のなかに、情報というキーワードをめぐる教育研究を「ヨコ糸」で縫い合わせてできた情報学環。教育部は、その情報学環という斬新的な東大の組織の特性を活かした、魅力的な学習の場となっています。
情報学環教育部では、毎年、前年度後期に入学試験をおこない、一学年約30名の教育部研究生を選抜します。大学2年生以上であれば、東京大学の学生だけではなく他大学の学生、社会人も含めて受験をすることができます(4月以降大学2年生になる見込みの人を含みます。ただし4月以降に大学院生となる見込みの人は含みません)。受験資格の詳細は募集要項を参照してください。
(引用:東京大学大学院情報学環ウェブサイト:情報学環教育部 – 東京大学大学院 情報学環・学際情報学府)
おや?これは……ずうずうしくも、もしや私にぴったり?
さっそくさまざま検索すると、どうやら大学院レベルの難易度と負荷ほどではなく、社会人も在籍している、学際的な学びの場とのこと。倍率は3倍程度の年が多く、入試は毎年2月と3月、2段階選抜のようでした。ということは、次の選抜は5ヶ月後。募集要項が秋に出て、翌年頭に出願が例年のスケジュールでした。
私は、ドキドキとワクワクが入り混じるような気持ちで、東京大学大学院情報学環の入試関連ページをブックマークしました。

穴があくほど応募要項をチェック!
まずはなにはともあれ、募集要項の確認です。Webに掲示された募集要項だけが私と大学院をつなぐ糸ですから、何が何でも読み解かなくてはなりません。ということで、紙で印刷して、マーカーを手に、真剣に読んでいきました。
1.出願資格
(1) すでに、大学(学部)に在籍している者 ただし、入学時において大学の2年次以上に在籍する者に限る。
(2) 大学を卒業した者 ただし、入学時(令和7(2025)年4月時点)に大学院に在籍している者は入学できない。 また、学部学生はその学部での学習に、有職者は勤務先の職務に支障がないものに限る。 なお、有職者の場合、勤務先との雇用契約上の問題については自らの責任において処理すること。
2.募集人員 約30名
(引用:東京大学大学院情報学環ウェブサイト:令和 7(2025)年度 東京大学大学院情報学環 教育部研究生募集要項)
どうやら私のような社会人でも応募できるようで一安心です。募集は30人と聞くと難しいかなと思いましたが、倍率のことは考えても仕方ありません。
次に選抜方法の確認です。ここが一番大切。一体どういう試験が課されるのでしょうか。
学習計画書(所定様式)
① 研究生になって学びたい事柄を3,000字程度(3枚)で記載すること。
② 2024年度の授業シラバスを検討し、履修してみたい授業を三つ選び、その理由を記載すること。
自己推薦書(所定様式)
・出願者自身の学業・職業・社会活動などの経験についてアピールしたい事柄を記載すること。
(引用:東京大学大学院情報学環ウェブサイト:令和 7(2025)年度 東京大学大学院情報学環 教育部研究生募集要項)
1次試験はこの書類によって判断され、2次試験はこれらの書類をもとに面接試験とあります。ということは事実上、この書類が一番大切……!
しかし、それまで研究と無縁だった私には、そもそも書式というかフォーマット、様式のようなものさえよくわかりません。
そこで、図書館に籠ってそういった研究計画書の書き方について速習しつつ、研究テーマを深く考えることに。私の場合はメディアや情報格差、教育といった分野と決めていたので、まずは社会情報学やメディアスタディに関する書籍や文献、論文を手当たり次第に読むことにしました。
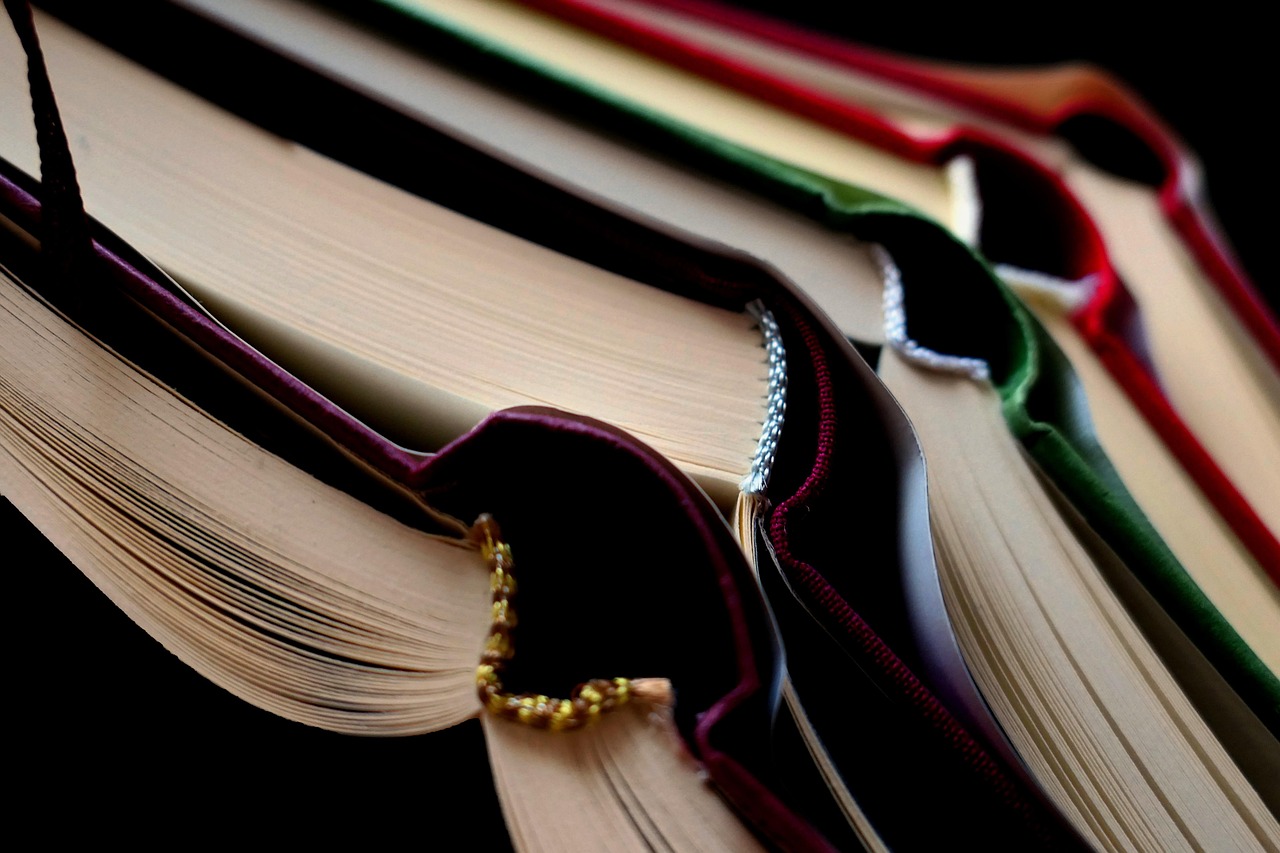
これはあまり効率がいい作業とは言えませんし、もっとご自身のやりたいことが定まっていれば必要のない作業だと思いますが、私はウォーミングアップも兼ねて、とにかくその分野の書籍を読みまくるという作戦を立てました。学術論文は今やインターネットで公開されていて、検索データベースがあり、教授やキーワードを入れればたくさん読むことができます。
近隣の図書館には、さすがに学術書は少なかったので、20年振りに学部を卒業した早稲田大学の中央図書館に突撃。身分証を提示すると卒業生は入場して本を読むことができました。おそらく他の大学も同様のところが多いと思いますので、ぜひ積極的に利用してみてください。

思うように勉強が進まない、社会人で母の受験生
さて、一通り視界が開けてきたところで、準備に全力投球……といきたいところでしたが、そこは3足のわらじのつらいところ。仕事がものすごく忙しく、かつ子どもの学校関連のあれやこれやに走りまわり、秋はまったく勉強ができませんでした。
頭の片隅に、1月になったら書類を提出なんだから、もっとスピードアップして勉強しなくちゃ、と意識はあるのですが、日々の怒涛に紛れて、腰を据えて勉強することができません。
家族には「ちょっと新春に向けて勉強したいことがあるんだよね~」とは言っていましたが、全員まったく本気にはしていなかったと思います。そんなこんなであっという間に年の瀬に……。いよいよ出願書類の提出締め切りが近づいてきました。
——次回は、怒涛のラスト1ヶ月の様子を報告させてください。











